
Information相続・終活お役立ち情報
相続発生後でもできる相続税対策~土地評価減による相続税の節税~

相続税は関与する税理士によって結果(税額)が大きく変わると言われることがあります。その理由は、税理士の技術によって土地の評価額に差が出るからです。合法的に評価されるのが大前提ですが、土地の評価額を下げれば下げるほど、相続税の金額を低く抑えることができます。
そのため、相続が発生した後(財産所有者の方が亡くなられた後)、土地評価に関して技術と経験が豊富な税理士を探して依頼することが、相続税対策として非常に大切になります。
今回は、対象となる土地について、評価のやり方によって評価額に差が出るのはどういった仕組みによるものか、税理士によって差が出る土地の評価の仕組みを解説します。
1.土地の相続税評価の基本
土地の評価は、主に住宅地や商業地等の市街地での評価方式である
①「路線価評価」
と市街化調整区域や都市郊外の地域で採用される評価方式である
②「倍率評価」
の2つの方法に分かれます。
①路線価評価
主に市街地を形成する地域での評価方法で、毎年7月1日に国税庁が発表する「路線価」に、評価対象地の地積を乗じて算定します。
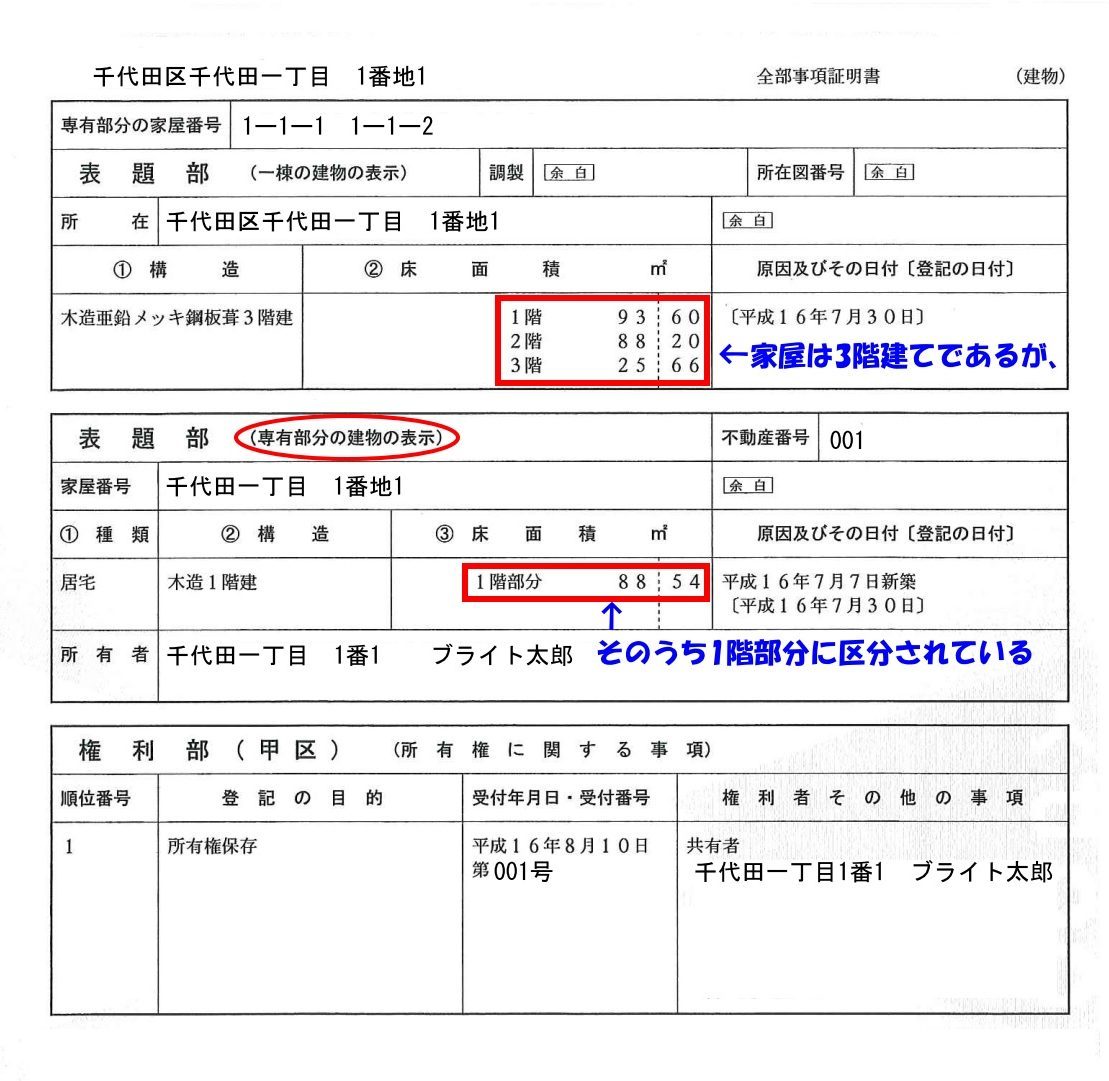
②倍率評価
都市郊外の地域で採用される評価方法で、毎年届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)に記載された固定資産税評価額に、毎年7月1日に国税庁が発表する「倍率表」に定められた倍率を乗じて算定します。
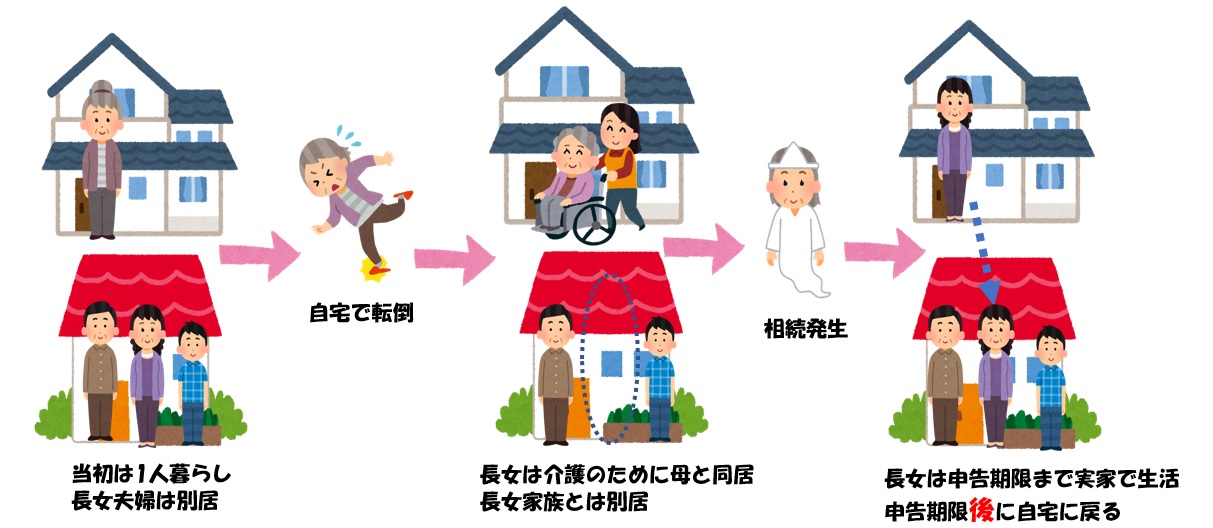
※上記の算式に基づく評価額は「自用地」(例えば自宅)の評価額です。
建物や土地を賃貸している場合や土地を賃借している場合には、「貸家建付地」、「貸宅地」、「借地権」として評価し、権利割合に応じた評価減を行うことができます。
2.土地の評価減のポイント
2つの方法のうち、関与する税理士によって、評価の仕方によって評価額に差が出るのは「路線価評価」の方法です。
前述の路線価評価の算式、「路線価×地積×対象地固有の補正率」のうち、「路線価」と「地積」については、どの税理士でも、また税理士でなかったとしても、容易に情報を入手することが可能で、ここで評価額に差が出ることはありません。
算式の中の「対象地固有の補正率」をどのように採用するかによって、評価額に差がでることになります。
以下の代表的な「補正率」をご紹介します。補正率は、その土地の評価の減額要因とも言えます。
| 不整形地(旗竿地など、形が不整形) | △1%~△40% |
| 地積規模の大きな宅地(500㎡以上など) | △20%~約△30%(面積によります) |
| 無道路地 | 最大△40% |
| 間口が狭小な土地 | △1%~△20% |
| 容積率が異なる2以上の地域にわたる宅地 | 異なるそれぞれの容積率と面積によります |
| 敷地内にがけ地がある宅地 | △4%~△47% |
| 私道 | △70% |
| セットバックが必要な土地 | セットバックが必要な部分について△70% |
| 都市計画道路予定地の区域内にある宅地 | △1%~△50% |
| 道路より高い(又は)低い位置にある宅地 | △10% |
| 墓地が隣にある土地 | △10% |
| 騒音がある土地 | △10% |
| 敷地内に庭内神しがある土地 | 庭内神し部分について非課税 |
| 宅地転用が困難な市街地にある山林 | △90%超の減額が可能なことも |
| 市街地農地等、造成が必要な土地 | 造成費の見積額を控除 |
| 高圧線下の土地 | △30%又は△50% |
3.土地の評価は奥が深い
上記の表は補正率の一例であり、実際の評価において検討する減額要因はより多岐にわたります。減額要因は法令・通達で明確に定められていないもの、専門書にも載っていないものもあります。
例えば「騒音がある土地」で評価を下げられると言っても、どれくらいうるさければ評価を下げてよいか、明確なルールがあるわけではありません。そのため、どの程度の音量であれば評価減が認められるか、ノウハウを心得ている相続専門の税理士を介し、過去の事例等を根拠として税務署に説明していくことになります。
その他にも、道路からどの程度高低差があれば評価減が認められるか、また、墓地からどの程度近くにあると評価減が認められるかなど、法令・通達での明確な基準のない場合においても、相続専門の税理士を介すことで、蓄積されたノウハウをもとに評価をしていくことになります。
また、土地の評価の際には、現地調査を行います。現地調査の際には、自分が対象地に住みたいかを想像します。住みたくないと思った部分があるとすると、それはどういった要因か、アンテナを立てておくことが重要になります。気づいた要因に基づく評価減を、根拠を示して税務署へ説明・立証していくことになります。

4.まとめ
いかがでしたでしょうか。相続税における土地の評価の奥深さと、税理士によって結果(相続税額)に差が出ることについて解説いたしました。
繰り返しになりますが、相続が発生した後(財産所有者の方が亡くなられた後)、土地評価に関して技術と経験が豊富な税理士を探して依頼することが、相続税対策として非常に大切になってまいります。
税理士法人ブライト相続 税理士 竹下祐史監修
Ranking人気記事
-

相続税の申告義務を把握する際の相続税の土地評価額をすぐ把握する方法について解説します!
-

自分で相続税申告ができるソフトをご紹介!メリットや申告の要否判定の方法とは?
-

【相続手続の手順】遺産相続手続のスケジュールを徹底解説!
-

相続人の調べ方を徹底解説!戸籍謄本の入手方法・必要書類は?
-

名義預金とは?該当するケースや対策方法をわかりやすく解説!
-

【ひな形あり】遺産分割協議書を自分で作成する方法とは
-

生前贈与とは?相続との違いやメリットは?
-

二次相続税を考慮した遺産分割の方法|事例をもとに徹底解説!
-

路線価とは?土地の価格の調べ方と計算方法を分かりやすくご紹介します!
-

「相続放棄の手続きは自分でもできる?」申請方法と相続税の計算における相続放棄の注意点を徹…


